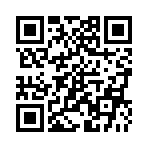2020年12月13日
新型コロナウイルス対策に悩む政治家、官僚の皆さん必読です。125年前、たった6ヶ月で23万人の検疫事業を行なった日本人
新型コロナウイルス対策に腰が引けている政治家や官僚の方々に、ぜひ見ていただきたい。
125年前、たった6ヶ月で23万人の検疫事業を行なった日本人を知っていますか?
1895年(明治28年)、日清戦争からの帰還兵23万人すべてを検疫、消毒、治療するという、
前代未聞、世界史上最大規模の検疫事業をやってのけた中心人物が、
岩手県奥州市水沢出身、のちの東京市長、後藤新平です。

先日奥州市前沢で、
後藤新平記念館の学芸調査員を講師に招いた講習会がありましたので、
資料をつけて紹介いたします。

後藤新平は1857年(安政4年)現在の奥州市水沢で生まれ、地元の塾で学び、
16歳で福島県須賀川医学校に入学。
医学校卒業後、医師として名古屋市の愛知病院に勤務し、
オーストリア人のローレンツ博士から西洋医学と衛生学を学びました。
なんと24歳の若さで愛知医学校長兼、愛知病院長に就任。
1883年、25歳で内務省衛生局に入り、
その後、ドイツ留学して衛生制度や社会政策を学び、
帰国して内務省衛生局長となりました。
その後、無実の罪を着せられ1年間浪人しましたが、
1895年(明治28年)、日清戦争が終わるや否や、
「臨時陸軍検疫部」創設の勅命が下り、その事務官長(現場の総責任者)に抜擢されます。
戦地から持ち込まれる未知の病原菌(コレラ・腸チフス・赤痢・痘瘡など)から日本国民を守る
これが後藤新平に課せられた任務でした。

現代の話ではありません。
明治維新から間もない125年前の日本で、
日本の3地域で海を埋め立て、木を切り払い、地ならしをし、
計400棟の建物を建て、電信、電話、電灯の設備を整え、、大消毒缶を製造して備え付けるのにたったの2ヶ月!

そこに日清戦争から帰還した船舶を迎え入れ、
1.船舶検査科=船内の検査、罹患者、死者の有無を確認
2.運搬科=小舟を遣わして人員、荷物、患者等の陸揚げ
3.沐浴科=健康な人員はことごとく消毒風呂に入れる
4.蒸気消毒科=巨大な蒸気消毒缶により、被服荷物で蒸気消毒に耐えうるものはすべて消毒
5.薬物消毒科=武器、携帯品、諸荷物等の蒸気消毒に耐えられないものを消毒
6.船舶消毒科=病毒汚染の疑いある船舶に対し、その全部、もしくは一部を消毒
7.焼却科=死体、汚物、及び物品の焼却
8.停留舎=輸送船内に一人でも発病者があって、病毒感染の恐れのある者は、一時停留舎に留められる
以上、作業を8つに分類し、
停留人の診断を行ない、伝染性の患者は直ちに避病院(隔離施設)に送り、
疑わしい患者は一時疑症室に移し、その結果、疑似の症状を呈したものは避病院に、
しばらくして治癒したものは、沐浴消毒の上、帰舎させるという業務でした。

帰還兵23万人
しかも戦争に勝って帰ってくる鼻息の荒い軍人に、
すべて検疫を受けさせるにはどうしたらよいか・・・??
後藤新平は、上司の臨時陸軍検疫部長、児玉源太郎に相談に行ったそうです。
児玉部長は、征清大総督として凱旋した皇族、小松宮殿下の船に乗り込み、
真っ先にお喜びを言上すると同時に、殿下に真っ先に検疫を受けて頂いたことで、
鼻息の荒かった軍人たちもすべてそれに従ったというエピソードも。
わずか4ヶ月で、
船舶総数687隻、総人数233,346人をすべて検疫、消毒、治療にあたり、
全消毒船舶16隻、局部消毒290隻
船内伝染病患者 コレラ369人 コレラ疑似313人 腸チフス126人 赤痢179人 痘瘡9人 計996人
停留人員46,699人という大事業を完了したのです。
下記は特に多数の死者を出した白山丸の惨状

蒸気消毒缶を開発したのは後藤の親友、北里柴三郎氏。
高木友枝医学士がコレラ血清を製造し、治療に用いたのはこの時が世界初とされています。
世界の歴史始まって以来の、この大検疫事業は、報告書が和文と英文で作成され、
陸軍省から欧米諸国に寄贈されましたが、
これを読んだドイツ皇帝が、この検疫の手際にいたく感心したことが報じられています。
後藤新平はこの検疫事業が完了した1895年(明治28年)9月、内務省衛生局長に復帰。
その後、
1898年(明治31年)40歳 台湾総督府民政長官
台湾人が今でも親日なのは後藤新平のおかげ?
1906年(明治39年)49歳 南満州鉄道総裁
1908年(明治41年)51歳 逓信大臣兼鉄道院総裁
1916年(大正5年)59歳 内務大臣兼鉄道院総裁
1918年(大正7年)60歳 外務大臣
1920年(大正9年)63歳 東京市長(現在の東京都知事)
1923年(大正12年)65歳 東京市長退職直後に関東大震災 内務大臣帝都復興院総裁
世界で初めて区画整理による都市計画を推進 現在の東京の骨格を作る
1924年(大正13年)67歳 東京放送(現NHK)初代総裁
ラジオ放送の普及に尽力
1929年(昭和4年)71歳 4月13日逝去
先見の政治家として、
明治維新後の日本の近代化に多大な功績を残しました。


後藤新平が詠んだ和歌
『ねさめよき、ことこそなさめ、なにわえの、 よしとあしとは、いふにまかせて』
あれこれ思い悩んで眠れないようでは良い仕事はできない。
これと思った決断は、世間の風評に惑わされることなく、自分を信じ実行するのがよい。
掲載した写真は文字が小さいですが、
お悩みの政治家、官僚の皆さん、マスコミの方々も、一字一句残さず読んでみてください。
「字が小さいから読めない」とか
「私のやったことじゃないから」なんて、人のせいにして文句を言う暇があったら、
後藤新平記念館から資料を取り寄せて学ぶ事ぐらいはできますね。
http://www.city.oshu.iwate.jp/shinpei/access.html
愚者は経験に学び、
賢者は歴史に学ぶ。
未知の病原菌から日本国民を守ってください
125年前に、これだけの大事業ができたのです。
現代にできない筈はありません。
125年前、たった6ヶ月で23万人の検疫事業を行なった日本人を知っていますか?
1895年(明治28年)、日清戦争からの帰還兵23万人すべてを検疫、消毒、治療するという、
前代未聞、世界史上最大規模の検疫事業をやってのけた中心人物が、
岩手県奥州市水沢出身、のちの東京市長、後藤新平です。

先日奥州市前沢で、
後藤新平記念館の学芸調査員を講師に招いた講習会がありましたので、
資料をつけて紹介いたします。

後藤新平は1857年(安政4年)現在の奥州市水沢で生まれ、地元の塾で学び、
16歳で福島県須賀川医学校に入学。
医学校卒業後、医師として名古屋市の愛知病院に勤務し、
オーストリア人のローレンツ博士から西洋医学と衛生学を学びました。
なんと24歳の若さで愛知医学校長兼、愛知病院長に就任。
1883年、25歳で内務省衛生局に入り、
その後、ドイツ留学して衛生制度や社会政策を学び、
帰国して内務省衛生局長となりました。
その後、無実の罪を着せられ1年間浪人しましたが、
1895年(明治28年)、日清戦争が終わるや否や、
「臨時陸軍検疫部」創設の勅命が下り、その事務官長(現場の総責任者)に抜擢されます。
戦地から持ち込まれる未知の病原菌(コレラ・腸チフス・赤痢・痘瘡など)から日本国民を守る
これが後藤新平に課せられた任務でした。

現代の話ではありません。
明治維新から間もない125年前の日本で、
日本の3地域で海を埋め立て、木を切り払い、地ならしをし、
計400棟の建物を建て、電信、電話、電灯の設備を整え、、大消毒缶を製造して備え付けるのにたったの2ヶ月!

そこに日清戦争から帰還した船舶を迎え入れ、
1.船舶検査科=船内の検査、罹患者、死者の有無を確認
2.運搬科=小舟を遣わして人員、荷物、患者等の陸揚げ
3.沐浴科=健康な人員はことごとく消毒風呂に入れる
4.蒸気消毒科=巨大な蒸気消毒缶により、被服荷物で蒸気消毒に耐えうるものはすべて消毒
5.薬物消毒科=武器、携帯品、諸荷物等の蒸気消毒に耐えられないものを消毒
6.船舶消毒科=病毒汚染の疑いある船舶に対し、その全部、もしくは一部を消毒
7.焼却科=死体、汚物、及び物品の焼却
8.停留舎=輸送船内に一人でも発病者があって、病毒感染の恐れのある者は、一時停留舎に留められる
以上、作業を8つに分類し、
停留人の診断を行ない、伝染性の患者は直ちに避病院(隔離施設)に送り、
疑わしい患者は一時疑症室に移し、その結果、疑似の症状を呈したものは避病院に、
しばらくして治癒したものは、沐浴消毒の上、帰舎させるという業務でした。

帰還兵23万人
しかも戦争に勝って帰ってくる鼻息の荒い軍人に、
すべて検疫を受けさせるにはどうしたらよいか・・・??
後藤新平は、上司の臨時陸軍検疫部長、児玉源太郎に相談に行ったそうです。
児玉部長は、征清大総督として凱旋した皇族、小松宮殿下の船に乗り込み、
真っ先にお喜びを言上すると同時に、殿下に真っ先に検疫を受けて頂いたことで、
鼻息の荒かった軍人たちもすべてそれに従ったというエピソードも。
わずか4ヶ月で、
船舶総数687隻、総人数233,346人をすべて検疫、消毒、治療にあたり、
全消毒船舶16隻、局部消毒290隻
船内伝染病患者 コレラ369人 コレラ疑似313人 腸チフス126人 赤痢179人 痘瘡9人 計996人
停留人員46,699人という大事業を完了したのです。
下記は特に多数の死者を出した白山丸の惨状

蒸気消毒缶を開発したのは後藤の親友、北里柴三郎氏。
高木友枝医学士がコレラ血清を製造し、治療に用いたのはこの時が世界初とされています。
世界の歴史始まって以来の、この大検疫事業は、報告書が和文と英文で作成され、
陸軍省から欧米諸国に寄贈されましたが、
これを読んだドイツ皇帝が、この検疫の手際にいたく感心したことが報じられています。
後藤新平はこの検疫事業が完了した1895年(明治28年)9月、内務省衛生局長に復帰。
その後、
1898年(明治31年)40歳 台湾総督府民政長官
台湾人が今でも親日なのは後藤新平のおかげ?
1906年(明治39年)49歳 南満州鉄道総裁
1908年(明治41年)51歳 逓信大臣兼鉄道院総裁
1916年(大正5年)59歳 内務大臣兼鉄道院総裁
1918年(大正7年)60歳 外務大臣
1920年(大正9年)63歳 東京市長(現在の東京都知事)
1923年(大正12年)65歳 東京市長退職直後に関東大震災 内務大臣帝都復興院総裁
世界で初めて区画整理による都市計画を推進 現在の東京の骨格を作る
1924年(大正13年)67歳 東京放送(現NHK)初代総裁
ラジオ放送の普及に尽力
1929年(昭和4年)71歳 4月13日逝去
先見の政治家として、
明治維新後の日本の近代化に多大な功績を残しました。


後藤新平が詠んだ和歌
『ねさめよき、ことこそなさめ、なにわえの、 よしとあしとは、いふにまかせて』
あれこれ思い悩んで眠れないようでは良い仕事はできない。
これと思った決断は、世間の風評に惑わされることなく、自分を信じ実行するのがよい。
掲載した写真は文字が小さいですが、
お悩みの政治家、官僚の皆さん、マスコミの方々も、一字一句残さず読んでみてください。
「字が小さいから読めない」とか
「私のやったことじゃないから」なんて、人のせいにして文句を言う暇があったら、
後藤新平記念館から資料を取り寄せて学ぶ事ぐらいはできますね。
http://www.city.oshu.iwate.jp/shinpei/access.html
愚者は経験に学び、
賢者は歴史に学ぶ。
未知の病原菌から日本国民を守ってください
125年前に、これだけの大事業ができたのです。
現代にできない筈はありません。